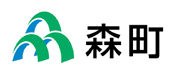猶予申請できる事例
猶予申請ができるケースについて事例をあげて説明します。
[事例1] Aさん(所有地550坪、地目 宅地) 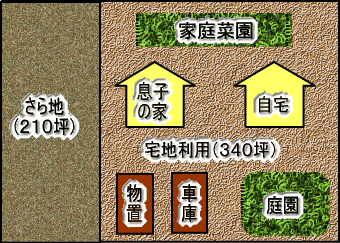
(ロ)の条件を満たします。
| 賦課面積 | ※340坪 | 550坪 |
| 猶予面積 | 210坪 |
宅地利用の面積が下限(300坪)をこえる場合は、その実面積が賦課対象面積になります。さら地は全部猶予です。
[事例2] Bさん(所有地550坪、地目 宅地) 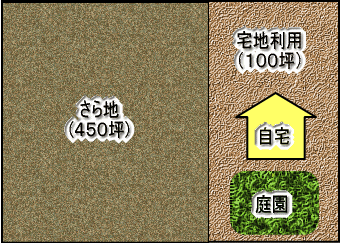
(ロ)の条件を満たします。
| 賦課面積 | ※300坪 | 550坪 |
| 猶予面積 | 250坪 |
宅地利用面積が300坪に満たない場合は、300坪を下限として賦課されます。したがって、さら地は一部猶予です。
[事例3] 下水道計画区域内で2ヶ所以上の土地所有者Cさん (所有地250坪+500坪、地目 宅地)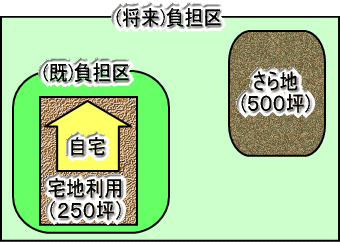
将来(ロ)の条件を満たします。
| 賦課面積 | (1) 300坪 | 1,000坪 |
| 猶予面積 | (2) 700坪 |
下水道計画区域内で2ヶ所以上の土地を所有する場合は、公平を期するため一括して猶予基準が適用されます。土地を合算すれば、将来を含めて300坪が賦課対象となります。250坪はその内数であるため、そのまま賦 課されます。しかし、将来負担区のさら地が負担区に編入された段階で、既負担区の土地が賦課済みであることが考慮され、賦課面積は300−250=50坪となります将来負担区の500坪に対して500−50=450坪が将来猶予されることになります。(ただし、その時点で猶予申請が必要です。)
[事例4] 居住地が農用地内にある農業者Dさん (所有地1,000坪、地目 畑)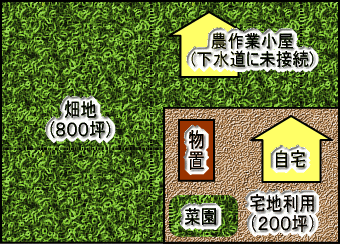
農業者(漁業者)の生活空間には規定があります。
| 賦課面積 | (1) 300坪 | 1,000坪 |
| 猶予面積 | (2) 700坪 |
居住地が農用地内にある場合は、生活空間(居宅、家庭菜園、庭園、物置場等)は300坪を下限として宅地利用と見なします。400坪の宅地利用の場合は、その実生活空間が賦課対象となります。
畑地による猶予面積は1,000−300=700坪となります。農用地内にある農業のための作業場、休憩場、物置場などは、当該建物の排水設備を下水道に接続する場合を除き、農地として徴収猶予されます。 漁業者が網干場、漁具干場、昆布干場等の用地として使用する土地も、農地の徴収猶予と同様に扱われます。